焚き火を始めるにあたって、一番最初に行うのが「火おこし」です。
火おこしって、出来ないときはとことん出来ないんですよね。私もキャンプ始めたばかりの時は非常に苦戦した記憶があります。
今回は火おこしのやり方を詳しく解説していきます。
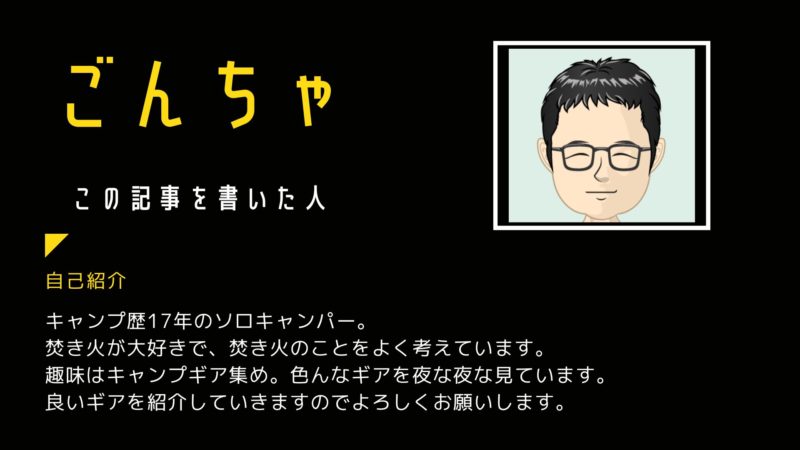
なぜ火おこしで失敗するのか
私の経験上、火おこし失敗の大半は、準備不足、もしくは必要な手順を踏んでいないことによるものです。
火おこしするにあたって準備は非常に大事です。準備無しで火おこしするのは、無防備で戦地に行くようなものです(ちょっとちがうか?)。
また火おこしには手順があり、順序を守らないことによって、上手く火が着かない、火が着いてもすぐ消えてしまうといったことになります。
環境による影響もある
火おこしは環境にも左右されます。
例えば、風が強い日だとすぐに火は消えてしまいますし、雨の日はそもそも着火が難しいです。
このような環境下は出来るだけ避けるようにし、どうしても避けられない場合は、対策を行って挑むようにしましょう。
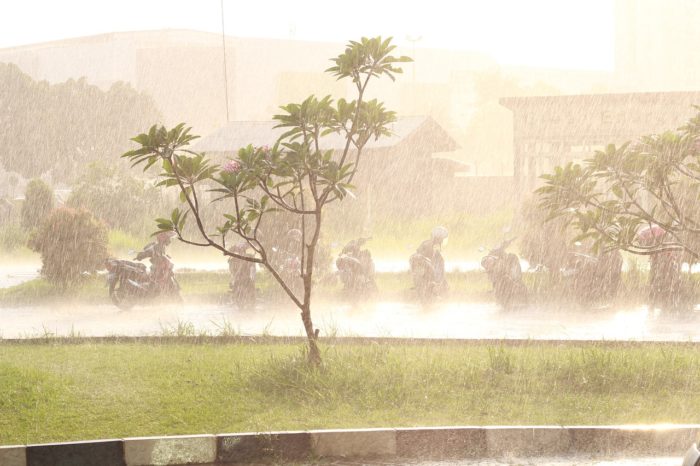
火おこしを成功させるには
火おこしを成功させるには、失敗しないこと。上で書いた失敗理由の対策をすればOKです。
準備をしっかりする、手順を守る、雨風の日は対策をする、といったものです。
火おこしは準備で決まる
火おこしは準備が第一です。火おこしの準備とは、必要なものを事前にしっかり揃えておくことです。
火おこしの準備で重要なのは以下の2つです。
- 着火剤・焚き付け用意する
- 燃えやすい薪の組み方をする
着火剤・焚き付けを用意する
着火剤は最初に火をつけるもので、非常に火が着きやすいものを指します。
この着火剤が無いと、火おこしのハードルはぐっと上がります。必ず用意しましょう。
市販品では、ジェルや木材繊維に油をしみこませたもの(文化たきつけ)があります。そういった市販品を使うもいいですし、松ぼっくり、枯れた杉の穂など、火の付きやすい天然の着火剤を使うも良しです。
焚き付けというのは、太い薪などへ着火させるための、燃えやすい枝や細い薪のことです。
薪の場合は、燃えにくいとされている広葉樹(ナラ、クヌギなど)ではなく、燃えやすい針葉樹(スギ、ヒノキなど)が適しており、針葉樹を焚き付けとして利用します。


燃えやすい薪の組み方をする
薪の組み方は非常に大事です。薪の組み方次第で燃えやすさが変わるので、火おこしを成功させるためには考えて組むようにしましょう。
薪の組み方は色々ありますが、燃えやすい組み方に共通しているのは「空気が入りやすい構造」です。
火が燃えるためには空気が必要で、空気が入らなければ火は着きません。また火は下から上へ行くものなので、下側にしっかり空気が入るようにする必要があります。
下側にしっかり空気が入るようなような組み方をすると、途中で火が消えることは無くなります。
火おこしは小さいものから大きいものが鉄則
火おこしの鉄則は、小さいものに着火し、徐々に火を大きくしていくことです。
薪に着火させる場合は、まず焚き付けにしっかり火をつけ、薪に移していくことが必要です。
着火剤 → 焚き付け → 細い薪 → 太い薪 の順序を守るだけでも、火おこしの成功率は大幅にアップしますよ。

火おこしの手順を詳しく解説
それでは実際に火おこしの手順を見ていきましょう。
まず最初に焚き火に必要な道具を準備します。
必要なものは、個人によって異なりますが、最低限以下は必要になると思います。
- 防炎シート
- 焚き火台
- ライター
- 燃料(着火剤、焚き付け、薪)
他は個人的に必要なモノや、環境、状況に応じて必要なものは+αで用意してください。
私の場合は、上記以外で以下道具も常時用意しています。
- ウィンドスクリーン
- 火消し壺
ウィンドスクリーンは風除け以外でも暖を取るのにも使えますし、火消し壺は素早く撤収したい場合に重宝します。

準備ができたら道具をセットしていきます。
防炎シートの上に焚き火台の組み立てます。防炎シートは、地面へのダメージを軽減する道具で、今は必須になっています。
直火OKのサイト以外では必ず使用するようにしましょう。

続いて着火剤をセットします。
着火剤は焚き火台の上に固めて置くのがポイントです。分散すると火力が弱くなり、焚き付けへの着火がスムーズにいかない場合があります。
今回は着火材に、麻紐と松ぼっくりを使います。

着火剤がセットできたら、焚き付けをセットします。
焚き付けは、着火剤に載せるような形で置きます。炎は下から上へ行くため、着火剤の上に置かないと燃えないためです。
今回は焚き付けに小枝を使用し、小枝をティピー型にして載せています。ティピー型は基本的な置き方で、よく燃えるのでおすすめです。
焚き付けを配置する場合は、着火口を開けて置くことを忘れないで下さい。開けておかないと着火時に後悔することになります。
また着火口を風上を向くようにしておくと、より空気が入りやすくよく燃えます。

手前側を着火口として開けておき、そこから着火していきます。
焚き付けがセットできたら、いよいよ着火するのですが、その前に燃料となる木や薪をセットしておきましょう。
着火剤や焚き付けは勢いよく燃えるのですが、すぐに燃え尽きてしまいます。
消えるまでの間に燃料を投入する必要があるため、焦らないようにこのタイミングで手元に置いておきましょう。

ここまで準備できたらいよいよ着火です。
着火口からライターを差し込んで着火材に着火してください。
ファイヤースティックを使う場合は、別途用意した着火剤に火をつけた後、火のついた着火材をセットした方の着火剤に持って行き火をつけます。
着火材に火がつき、焚き付けへ火が燃え移ると思います。


この時点で焚き付けに火が移り、大きく火が上がっていると思います。
この火が大きく上がっているタイミングで、用意しておいた細い木・薪から投入し、火を安定させます。
細い薪に火が付くと、なかなか消えないので、ゆっくりと楽しむ時間ができます。

細い薪が燃え始めるともう安心です。頃合いを見て太い薪を入れてください。
あとはひたすら焚き火を楽しむ最高の時間が待っています。

まとめ
いかがでしたか。火おこしって簡単だ、というのが伝わったでしょうか。
準備と薪の組み方さえしっかりすれば、火おこしは失敗することなく、簡単に成功します。
しっかりと準備し、スマートに火おこしを決めましょうね!
- 火おこしは準備で決まる
- 火おこしは小さいものから大きいものへ火を移していく
- 空気の流れを意識すれば失敗しない
それでは!
↓応援のポチしていただけると嬉しいです!↓
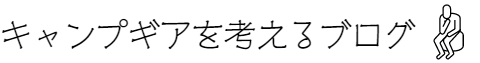










コメント